迅速な出産手当金
「出産手当金に関して」SNSで目立っている呟きを調べてみた。
「何が申請書に必要なのか」、「どれくらい貰えるのか」などという前に「私も貰えるのか」、「どこに申請するのか」、「会社に妊娠を伝えればやってくれるのか」と制度の基本的理解が乏しい人も多いことに愕然。
そして、何といっても、「支給が遅いこと」への怒りが圧倒的に多い。
その内訳は、「会社が主体的にやってくれると思ってたら何もやってくれてない」から「私が書類出しても会社が処理して呉れてない」、「会社が提出済みと言ったので協会・組合に聞いたら提出されてなかった」「会社が社労士任せでその社労士がいい加減」と様々。そして、「産後2ケ月経っても支給されない」、「産休期間(14週間)プラス支給期間は無給で、暮らせない」と。
確かに、育児休業給付金関連のように新制度導入という遅れる要因は無いのに、出産10月後というのは、被保険者、会社、社労士、協会・組合、制度、一体誰が悪いのか?(忘れてはならないのは、間に入った社会保険労務士の怠慢に対する批判も多いことだ。会社が正直でないこともあると推測されるが、直接社労士と交渉したとする被保険者たちからの批判の声もある。)
けんぽ協会は申請受付から振込まで10日以内の目安を示し、令和6年の現金給付(傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬費)の実績平均所要日数は5.63日と迅速でした。申請先が健康保険組合の場合は、協会けんぽよりかかっているようで実情はそれぞれである。
そこで申請から支給の流れを中心に、早期給付について考察してみた。
・まずは、妊娠・産休時に会社との会話が貧困でかつ健康保険制度への理解が不足しているケース。
会社も「給料支払いがない間、税などの徴収をどうするか」や産休後の育児休業及び給付金申請についても合意するとともに、被保険者休業中の職場の体制整備が必要です。
現状では、会社が小規模などで事務処理能力がなかったり給付申請に積極的でない場合は、待っておられず被保険者が自分がやるっきゃないというケースもありがちです。
・次に、申請制度の流れを検討してみる。
給付申請は、産後休業終了後が原則なので出産日の8週間以降になる。
申請にはその期間の勤務状況(休んだこと)、賃金支払いがなかったことの事業所の証明が必要です。
けんぽ協会は、申請書(令和6年度郵送申請95.8%)にこの状況を記入し、出勤簿や賃金台帳の写し等書類は(事務効率化のため)原則求めていない。一方、健保組合は求めるところが多いようだ。その場合、賃金締日と支払日の間が長いと対応した期間の賃金台帳作成が遅れ、その間申請できず早期支給のネックとなっている。
申請期間単位は、産休一括と産前・産後分割パターンで、健保組合によっては一括パターンだけのところもあるよう。産後一括だと、通常、産前から98日以降の申請になるが、分割だと56日は短くできる。
医師の証明は、出産前に産前分申請時には出産予定日(計画分娩等で変更になった場合も初回検診時の予定日)、出産後の申請時には出産日の証明(申請書に記載)がないと支給申請できません。出産後の産前一括申請時は、両方証明できるので、産後分の申請時には医師証明は不要となります(健康保険組合については要確認)。
振込先は、原則、けんぽ協会は被保険者、健保組合は会社経由です。
・出産手当金の早期支給のための改善案として
●会社・被保険者に、国・地方公共団体からメリットを与え積極的にさせる。
・ハローワークの事業所情報のなかに出産手当金等の給付実績記載欄を設ける
・小規模企業に対する5000円程度の申請事務報奨金
・被保険者の市への妊娠報告時に「お礼カード(受給者から会社へ支給事務に対し)」や「申請確認カード(出産・産後終了、会社へ申請書提出、社労士事務所依頼、申請書提出・決定・振込(会社・被保険者)の日付チェック・無給期間・資金繰り)」を交付
●健康保険組合に対して、国の監査視点に給付の迅速性(出産日から出産手当金振込迄の所要日数改善)を加えるとともに、毎年給付までの所要日数をHP公表を義務付けさせる。
産前・産後休業の日数算出方法に関しては、次のような通達が出されています。
(昭和23年12月23日基発1885号、昭和26年4月2日婦発113号)
この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶並びに、死産の場合も含む
(昭和25年3月31日基収4057号)
実際の出産日が予定日後である場合、休業期間はその遅れた日数分延長される。なお、出産当日は「産前」に含まれる。
(昭26.4.2 婦発113号)
産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。
・申請書への医師証明(文書作成料)は、医療機関によって自由に定められる「自費診療」にあたるが、3000~5000円が多いようだ。
令和6年 10 月の出産手当金受給者全員を調査対象(19,781 件)
年齢階級別支給件数の構成割合は、 30~4 歳が 37.75%、次いで 25~9 歳(29.38%)が多い。
1件当たり支給日数の平均は 83.39 日、1件当たり金額の平均は 454,245 円。
出産手当金の支給件数について標準報酬等級別の構成割合をみると、18 級(220 千円)が13.38と最も多い。
令和5年度の出産手当金の給付費は総額908億円で、平均1件当たり日数84.08日、1件当たり445,546円、1日当たり5,299円となっている。
出産一時金の給付費は、被保険者分1012億円、被扶養者分559億円の支出。
令和5年度末(6年3月 31 日)現在に存在した 1,380 組合について、集計
出産手当金の給付額は、655億円、出産一時金の給付額は、被保険者分652億円(1件当たり485,174円)、被扶養者分428億円(1件当たり48,601円)の支出。

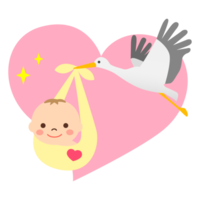


コメント